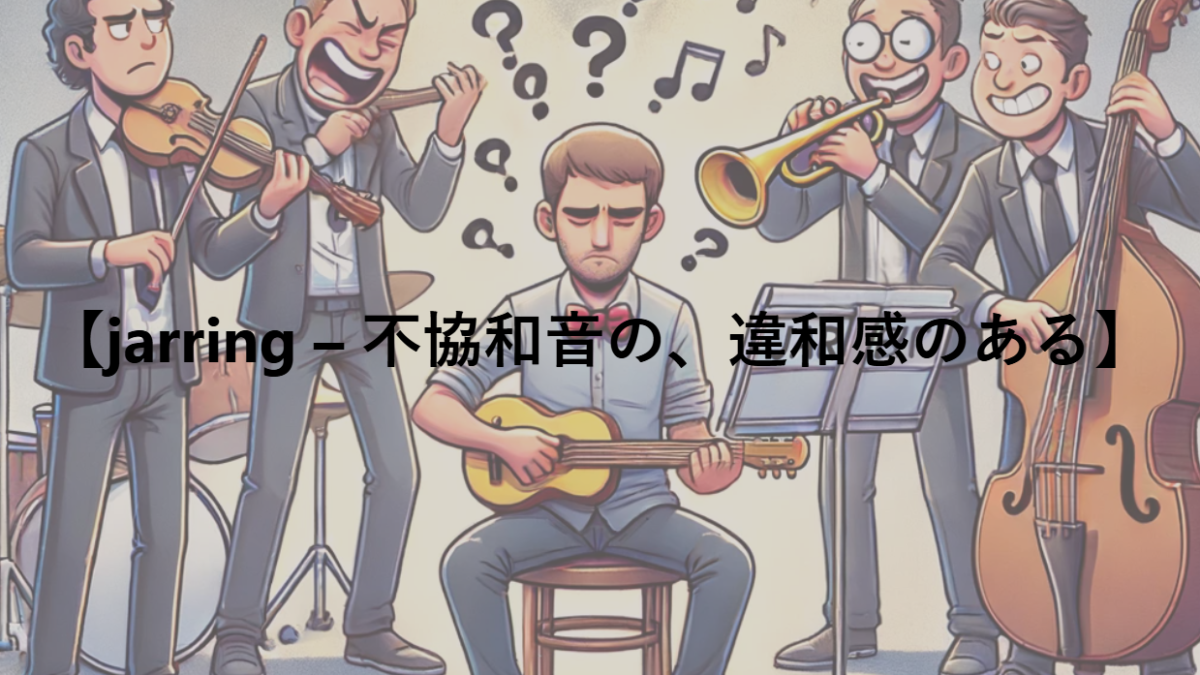「調和を乱す jarring、耳と心に響く不協和音」
📚 意味と用法
jarring は、形容詞として「耳障りな」「不調和な」「衝撃的な」という意味で使われます。音が不快で調和を乱す場合や、突然の変化や対比が心地悪い印象を与える状況を表現します。また、物理的な衝撃や振動による「震動を与える」という意味もあります。
音に関する用法 (Sound-related usage)
The jarring sound of the alarm clock woke me up abruptly.
(目覚まし時計の耳障りな音が私を突然起こした。)
体験・変化に関する用法 (Experience/Change usage)
The jarring contrast between wealth and poverty was evident in the city.
(富と貧困の衝撃的な対比がその都市では明らかだった。)
🕰️ 語源と歴史
「Jarring」は、動詞「jar」の現在分詞形です。「jar」は中世英語の「jarren」に由来し、「震動させる」「衝撃を与える」という意味を持ちます。この語は擬音語的な起源を持ち、物が激しく当たったり震えたりする音を表現していました。
16世紀頃から「不調和な」「耳障りな」という比喩的な意味で使われるようになり、現代では音響的な不快感から心理的な不快感まで幅広く表現する形容詞として定着しています。
🔄 類義語 (似た意味の言葉)
言葉のニュアンス
| jarring | 突然の不快な感覚や調和の破綻を強調 |
| harsh | 厳しさや刺激的な性質を強調 |
| grating | 継続的なイライラや不快感を強調 |
⚡ 対義語 (反対の意味)
対照的な使用例
jarring な音は調和を乱しますが、harmonious な音は心地よい調和を生み出します。soothing な音楽は心を落ち着かせる効果があります。
💬 実践的な例文
The jarring sound of construction work disturbed the peaceful neighborhood.
建設工事の耳障りな音が平和な住宅地を乱した。
The transition from classical music to heavy metal was quite jarring.
クラシック音楽からヘビーメタルへの移行はかなり衝撃的だった。
Her jarring laughter broke the silence of the library.
彼女の耳障りな笑い声が図書館の静寂を破った。
The jarring contrast between the modern skyscrapers and old buildings was striking.
現代の高層ビルと古い建物の衝撃的な対比が印象的だった。
The sudden change in his behavior was jarring to his friends.
彼の行動の突然の変化は友人たちにとって衝撃的だった。
🧠 練習問題
以下の空欄に入る最も適切な単語を選んでください。
1. The ______ noise from the construction site made it impossible to concentrate.
解説:
建設現場の騒音で集中できない状況では、「耳障りな (jarring)」が最も適切です。
2. The ______ contrast between the rich and poor areas of the city was shocking.
解説:
富裕層と貧困層の地域の衝撃的な対比を表現するには「jarring」が適切です。
3. Which of the following is NOT a synonym of “jarring”?
解説:
“Soothing” (心地よい) は「jarring」の対義語であり、類義語ではありません。
4. The sudden change from soft music to loud rock was quite ______.
解説:
音楽の急激な変化による不快感を表現するには「jarring」が適切です。
5. The word “jarring” comes from the verb “jar” which means to ______.
解説:
「Jar」は「震動させる」「衝撃を与える」という意味で、「jarring」の語源です。